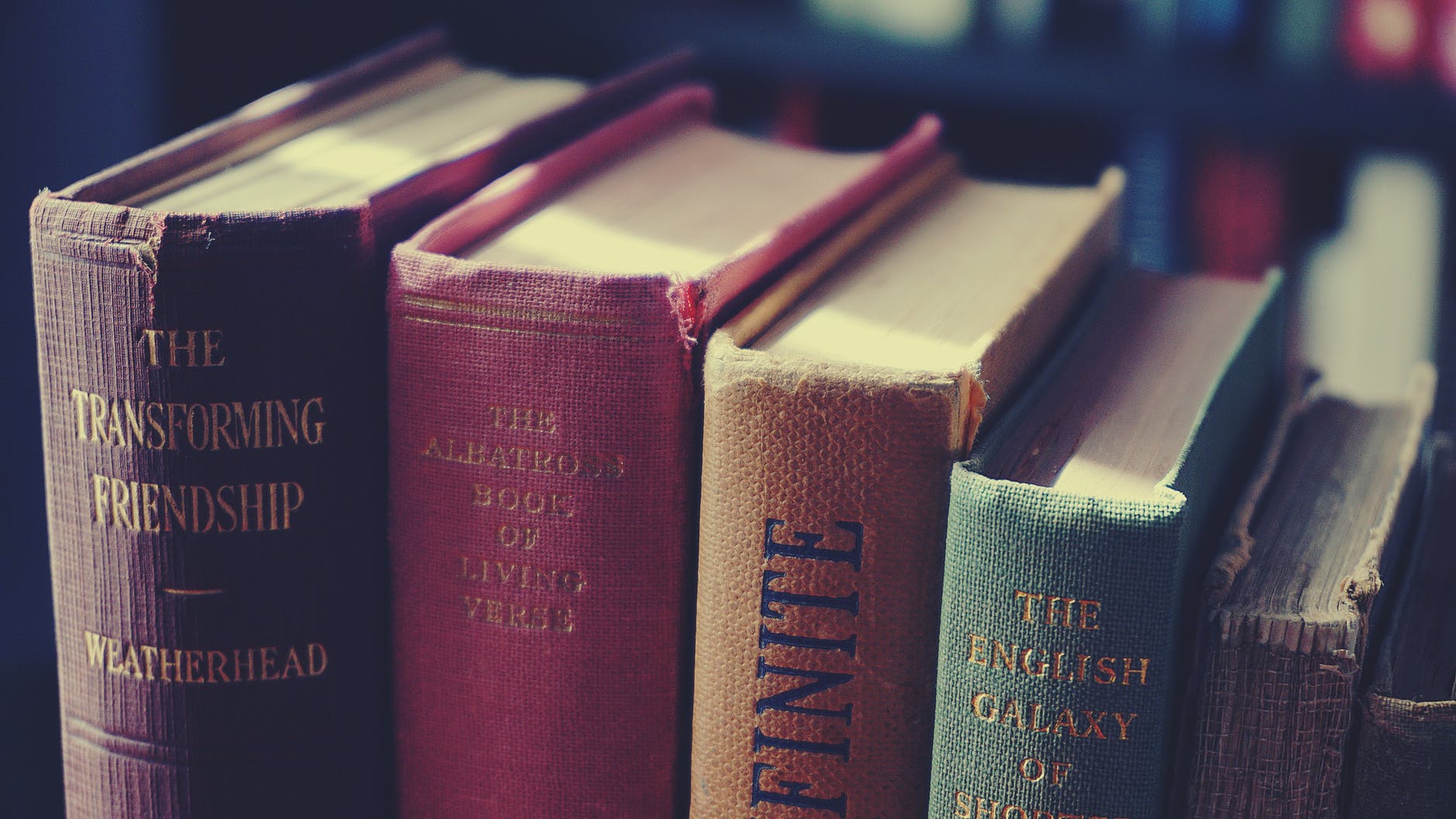今なら入会金無料!(先着5名)
AO-FILEではAO/総合型選抜オンライン専門塾「AO-Online」を運営しています。
大手AO対策塾の指導実績があり、中でも特に高い実績をあげた講師たちが全力で合格をサポートいたします。内部でしかわからない情報、合格者の志望理由などをお見せすることも可能です!!
AO合格には、AOに精通している人しか知らない”合格のコツ”があります。そんなコツを知りたい人はこちらから無料相談へ!!
AO-Onlineは、日本初の完全オンラインAO/総合型選抜専門個別塾です。
AO-Onlineでは、AO/総合型選抜対策として、AO/総合型選抜で難関大に合格し、豊富な指導実績のある選りすぐりの講師が書類対策(志望理由書、自己推薦書、自由記述書、課題レポート、自己PR書類など)、小論文対策、面接対策をはじめ、AO受験の受験戦略の策定や志望理由書のテーマ決め、研究指導などを徹底的に行います。これらの内容を各生徒様に合わせて、完全個別にカスタマイズしてお届けできるため、無駄が一切ない質の高い授業をお届けできます。
まずは無料相談から
AO-Onlineでは現在無料相談を実施しております。
無料相談では
「AO/総合型選抜ってそもそも何?」
「AOと一般受験の両立ってできるの?」 といったお悩み相談から、 各個別の生徒様にあったAO指導まで幅広い形で授業を行うことが可能です。
体験授業が完全無料ですので、AOについてもっと知りたい、ひとまず対策方法について聞いてみたいといった人でも まずはお申し込みください。
AO Onlineをもっと知る
AO Onlineの無料体験授業はこちら